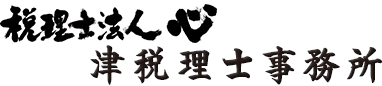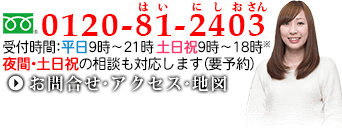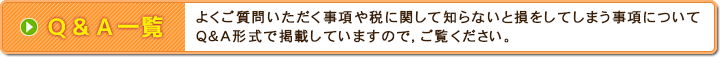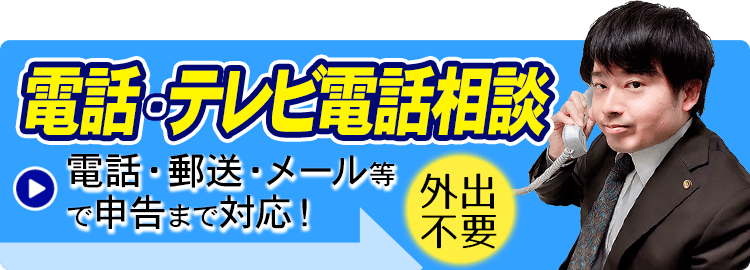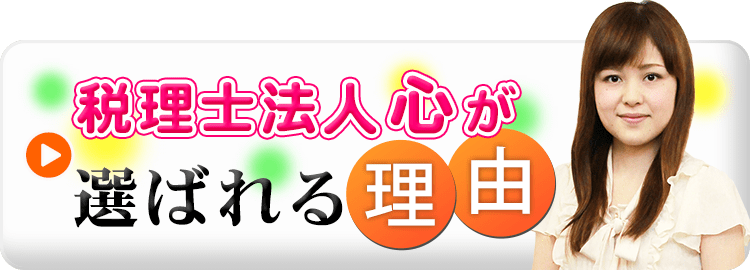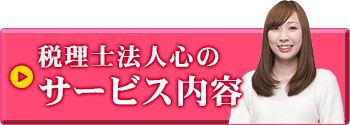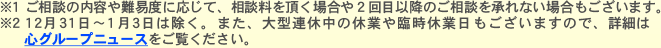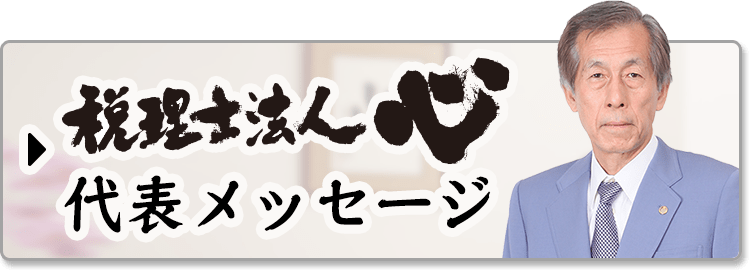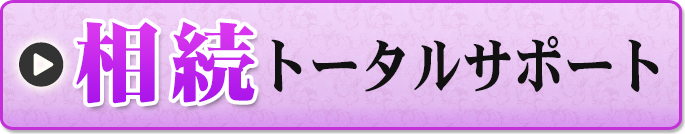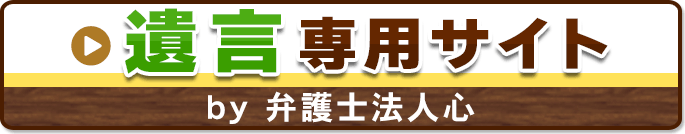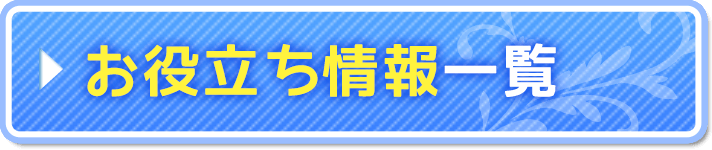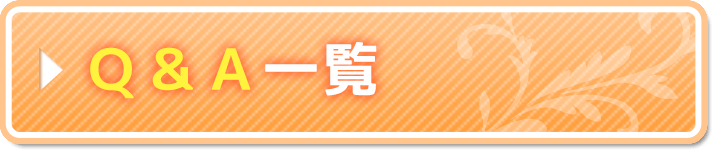期限までに相続税申告が間に合わない場合
1 相続税申告の期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月後と定められています。
多くの場合は、被相続人が死亡した日に被相続人が亡くなったことを知ることになりますので、実質的には被相続人が亡くなった日から10か月後が申告期限になることが多いといえます。
2 相続税申告が期限に間に合わないケース
⑴ 時間が足りないケース
相続税の申告を行うためには、相続人や相続財産の調査を完了させた上で、相続税の申告書を作成する必要があります。
10か月間というと、長い期間のように思えるかもしれませんが、実際にこれらの準備を行うと、10か月の期間は意外に短く感じます。
この10か月間、相続税申告の準備だけできるのであればよいのですが、実際にはそうもいかない場合が多く、なおさら短く感じるかと思います。
このため、現実には、申告期限の直前になっても、相続税申告の準備が整っていないといったことが起こる可能性があります。
⑵ 後から多額の財産が発覚したケース
また、当初は相続税が課税されないと思って特に準備をせずにいたものの、申告期限の直前になって多額の財産が発見され、相続税の課税対象であると判明することもあり得ます。
このようなケースであっても、被相続人が亡くなったこと自体は知っていたのであれば、通常どおり10か月の期間が経過すれば、相続税の申告期限を迎えてしまうことになります。
⑶ 申告の制度自体を知らなかったケース
さらには、相続税の申告という制度自体を知らず、何もせずにいたところ、申告期限の直前になって、相続税の申告をしなければならないことを知ったというケースも起こり得ます。
このように、たとえ法を知らなかったとしても、申告期限が延長される等の救済措置はありません。
以上のように、相続税の申告の準備を十分に行うことのないまま、期限の直前になってしまい、期限までに相続税申告の準備が間に合わないといった相談を頂くことは、しばしばあります。
3 申告することなく申告期限が経過した場合
このような場合に、申告することなく申告期限が経過してしまうと、いくつかのペナルティが課されることとなります。
まず、申告期限が経過した時点で相続税の申告がされていなかったことを理由として、無申告加算税が課税されます。
次に、申告期限後、相続税を納付するまでの期間について納税が遅延したことに対して、延滞税が課税されます。
このため、申告することなく申告期限が経過してしまうと、本来の相続税に加えて、無申告加算税、延滞税といった増額された税金も納付する必要が生じることになり、大きな負担となってしまいます。
4 申告期限内での対処法
それでは、このようなペナルティを避けるためにも、申告期限内に、どのような対処を行うことが考えられるのでしょうか。
まず、無申告加算税の課税を避けるためには、概算でも構いませんので、相続税の申告書を作成し、期限内に提出することになります。
概算であっても、相続税の申告書を提出しさえすれば、無申告加算税の課税を避けることができます。
次に、延滞税を避けるためには、概算で申告する際、多めに申告するという対処法が考えられます。
申告・納付した税額が本来の税額よりも過少である場合には、一旦、申告・納付をしていたとしても、過少申告加算税、延滞税が課税されてしまいます。
そのため、こうした事態を避けるためには、概算で申告する際には、多めに申告を行い、納付した税額が本来の税額よりも多くなるようにするのがよいと思われます。
このように、一旦は概算で当初の申告を行っておけば、後日、税額を計算し直して正確な申告書を作成し、申告書を提出し直すことができます。
先述のとおり、当初の申告を多めの税額で行っておけば、更正の請求を行うことによって、納め過ぎた相続税の還付を請求することもできます。
参考リンク:国税庁・相続税及び贈与税の更正の請求手続
生命保険について契約者貸付がなされていた場合の相続税 遺留分と相続税