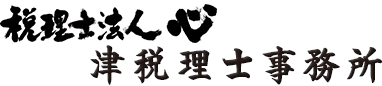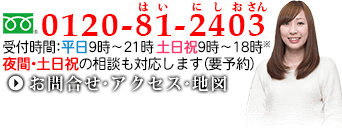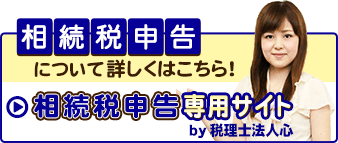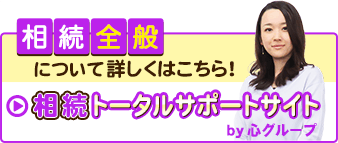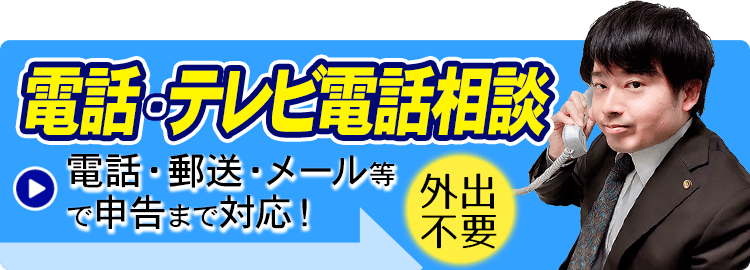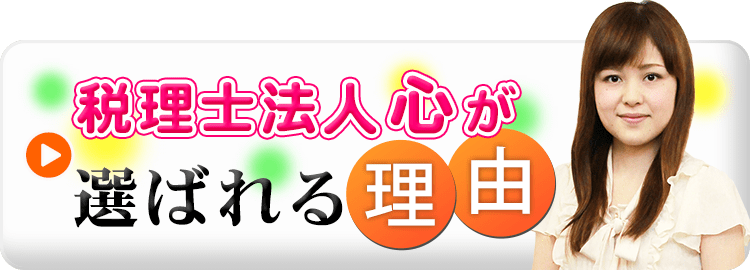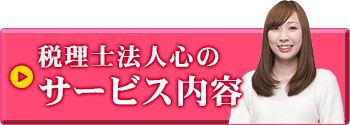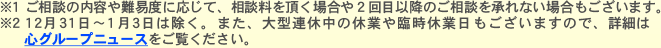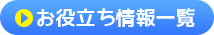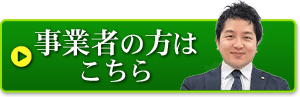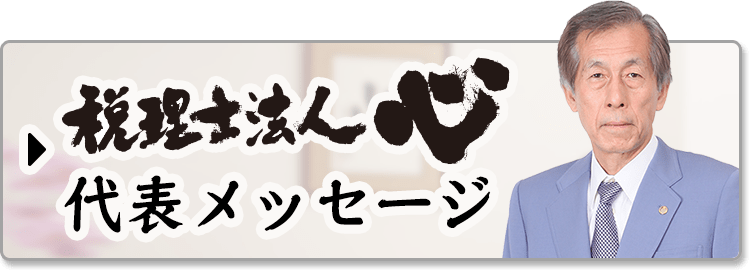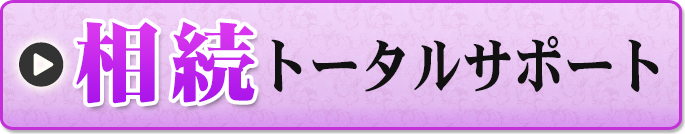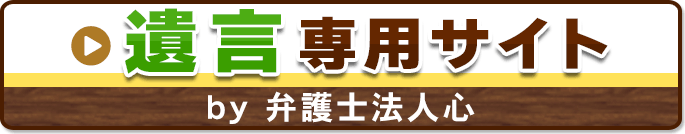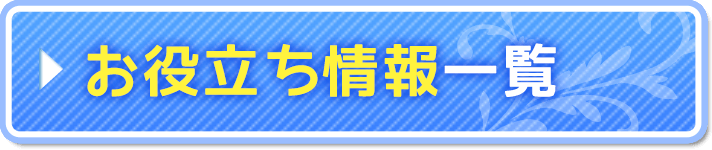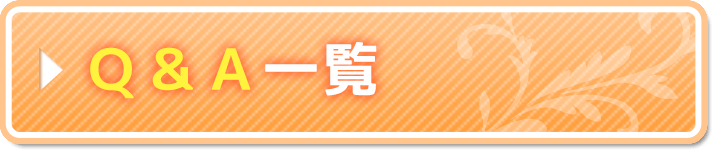相続税申告(相続発生後)
相続税申告を必要とされるお客様の手続を代行いたします。
相続した財産や生命保険金について,相続税が課税されることがあります。
具体的には,相続財産の評価額や生命保険金の額(相続人1人ごとに500万円の非課税限度額を超える額)の合計から,被相続人の債務や葬儀費用の額を差し引いた金額が,基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合には,相続税が課税されることとなります。
このような場合には,被相続人が亡くなられたことを知った日(通常は被相続人が亡くなられた日)の翌日から10ヶ月以内に,相続税の申告書を提出するとともに,相続税の納付を行う必要があります。
相続税の申告をしなければならないものの申告の仕方が分からない方,相続税の申告が必要かどうかが分からない方は,当法人までお問い合わせください。
税理士法人心では,相続財産の評価を行い,相続税が課税されるかどうかを検証し,相続税が課税される場合には,申告書等の手続を代行いたします。
相続税についてお悩みの方へ
1 相続税はどの税理士に相談するかが重要

相続税は、どの税理士に相談するかによって、大きな違いが出てくる税目です。
特に、相続税に詳しい税理士かそうではない税理士かは重要なポイントです。
ここでは、相続税について、税理士によってどのような点で違いが出てくるかについて、説明したいと思います。
2 評価結果の違い
相続税の申告にあたっては、個々の財産について、評価額を算定する必要があります。
このような財産評価のルールについては、財産評価基本通達等において定められています。
もっとも、財産評価基本通達等の規定は、多岐に渡っています。
このような規定を詳細に把握し、個別の事案でどこまで用いることができるかによって、評価結果は大きく異なってきます。
たとえば、土地については、奥行価格補正、間口狭小補正、不整形地補正等の補正計算をきちんと行われているかどうかが、最初の分かれ目になってきます。
次に、都市計画法、土砂災害防止対策の推進に関する法律、農地法等の特別法の規定を踏まえ、修正計算が行われているかどうかも重要になってきます。
さらには、公衆用道路の一部になっている土地、利用価値が著しく低下している宅地等、現地の状況を踏まえた修正も大切になってきます。
これらは、すべて、財産評価基本通達等において規定が設けられていますが、実際に申告にあたってこれらの規定を用いることができるかどうかは、別問題です。
この点は、相続税に詳しい税理士であるかどうかによって大きく異なってくる部分です。
3 申告までのスピードの違い
相続税に詳しい税理士であれば、どのような資料を収集すべきか、どのような申告書を作成すべきかを一通り把握していますので、これらの段取りをスムーズに行うことができるでしょう。
まだ、一通りの税法のルールを把握しているでしょうから、税法のルールを一つ一つ確認する必要も少ないでしょう。
このため、相続税に詳しい税理士であれば、申告の準備に要する期間が短く、迅速に申告できる可能性が高まります。
また、最低限のやり取りで、資料収集、申告の作成を行うことができ、この点でも時間短縮になると言えます。
4 税理士へのご相談
相続税の申告を適切かつ迅速に行うためには、どの税理士に相談するかが重要なポイントになってきます。
当法人は、税理士が税目ごとに特化して申告を行い、より適切かつ迅速な申告を行えるよう、体制を構築しています。
相続税についてのお悩みがありましたら、当法人にご相談いただけましたらと思います。
相続税の申告の期限
1 相続税の申告・納付とは

相続税が課税される場合には、相続税の申告と納付を行う必要があります。
相続税の申告は、申告書を管轄税務署に提出することを言います。
相続税の納付は、申告書で計算された相続税を納めることを言います。
2 相続税の申告・納付の期限
相続税の申告と納付は、相続が起きたことを知ってから10か月以内に行う必要があります。
厳密には、被相続人が死亡した日から10か月ではなく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月です。
このため、被相続人が死亡したことを知らなかった場合には、10か月の期間はカウントされないこととなります。
もっとも、税務署は、基本的には、被相続人が死亡した日から10か月間に申告・納付がなされているかどうかをチェックしていますので、被相続人が死亡した日から10か月以内に申告・納付の手続を終えた方が安心でしょう。
3 申告書の提出方法
先述の相続税の申告期限までに、相続税の申告書を作成し、提出する必要があります。
どのようなことを行えば提出したものと扱ってもらえるかについては、提出方法によって異なります。
税務署に直接提出しに行く場合は、午後5時までの窓口時間に、窓口で受け取ってもらうのが良いでしょう。
午後5時以降になってしまった場合は、日を越す前に夜間ポストに提出すれば、その日に提出したものと扱ってもらえます。
郵送で提出する場合は、郵便物として発送すれば、発送したときに提出したものと扱われます。
発送を申告期限までに行えば、税務署に到達したのが申告期限後であったとしても、申告期限内に提出したものと扱われます。
ただし、郵便物以外の方法で、具体的には、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットで送付した場合には、発送したときではなく、税務署に到達した時に提出したものと扱われますので、注意が必要です。
e-Taxで提出する場合、送信の時点で提出したものと扱われます。
正常に送信されたかどうかは、メッセージボックスで確認することができます。
4 申告書の提出先
申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所地を管轄する税務署が提出先ではありませんので、注意しましょう。
税務署によっては、国税局の業務センターも提出先に指定していることもあります。
保証債務、連帯保証債務と相続税の債務控除
1 保証債務とは

保証債務は、主債務者が債務を返済できない場合に、保証人が代わりにその債務を返済する責任を負うことをいいます。
主債務者が債権者に対して約束どおり返済を行っている間は、債権者が保証人に対して返済を求めることはありませんので、保証債務の問題が表面化することはありません。
ところが、主債務者が債権者に対する返済を行わないようになると、債権者は、保証人に対して、代わりに返済をするよう請求してくることとなります。
保証人は、保証債務を負っている以上は、債権者のこのような請求を拒むことはできません。
このような債務については、一定以上、債権者に対する返済が行われなければ、期限の利益を喪失するとの条項が設けられていることが多いです。
つまり、一定以上、債権者に対する返済が行われなければ、未返済の債務の全額について、一括して返済することを求められることとなります。
このように、保証人は、主債務者の代わりに債務を返済しなければならないという点で、極めて重い責任を負っていることとなります。
2 連帯保証債務とは
保証債務と似た言葉で連帯保証債務という言葉が使われることがあります。
連帯保証債務は、保証債務とどのような違いがあるのでしょうか?
保証債務については、債権者は、主債務者が返済をしなかったとしても、すぐに保証人に対して請求することができるわけではないこととなっています。
保証人は、債権者に対して、まずは主債務者に対して請求するように求めることができますし、まずは主債務者の財産から取立を行うよう求めることができます。
これを、催告の抗弁と検索の抗弁といいます。
債権者がこれらの要求に応じない場合には、保証人は、債権者に対し、返済を拒むことができます。
これに対して、連帯保証債務の場合は、催告の抗弁と検索の抗弁が存在しません。
このため、連帯保証債務については、債権者は、主債務者が返済しない場合には、すぐに連帯保証人に対して請求することができることとなっています。
このように、法律上は、連帯保証債務は、保証債務よりも、より重い責任を負うこととされています。
他にも、分別の利益がない等の違いもありますが、それ以外の点は、保証債務と連帯保証債務との間では、違いがないこととなっています。
3 保証債務、連帯保証債務は債務控除の対象になるか
相続税の計算方法は、おおむね以下のとおりです。
① 被相続人のプラスの相続財産の総額を算定
② ①から、被相続人が負っていた債務を差し引く
③ ②に、課税価格に応じた税率を乗じる
このように、相続税の計算上、被相続人が負っていた債務は、被相続人のプラスの相続財産から差し引くことができることとなっています。
それでは、保証債務、連帯保証債務については、相続税の計算上、被相続人が負っていた債務として、被相続人のプラスの相続財産から差し引くことはできるのでしょうか?
債務控除の対象となるのは、確実と認められる債務に限られています。
保証債務、連帯保証債務については、主債務者が返済を行わない場合に、保証人、連帯保証人が返済しなければならなくなるとされています。
基本的には、主債務者が返済を行うか行わないか、引いては、保証人、連帯保証人が返済しなければならなくなるかどうかは、不確実であると考えられます。
このため、保証債務、連帯保証債務については、一般的には、債務控除の対象とすることができないこととされています。
とはいえ、諸般の事情から、主債務者が返済を行わず、保証人、連帯保証人が返済しなければならなくなることが確実であるといえる場合は、保証債務、連帯保証債務を債務控除の対象とすることができます。
もっとも、確実といえる場合については、税務署は、主債務者が弁済不能の状態にあり、かつ、主債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みがない場合に限るとしており、かなり限定された場合にしか債務控除を行うことはできないこととされています。
具体的には、個人の主債務者ですと、継続的に返済を行っておらず、かつ、不動産、預貯金、有価証券等の資産を有していない場合、法人の主債務者ですと、 継続的に返済を行っておらず、債務超過に陥っている場合に限られることとなっています。
配当期待権、未収配当金と相続税
1 配当と相続税

被相続人が株式を保有していることがあります。
この場合、株式は、相続税の課税対象になりますので、きちんと評価を行い、申告書に記載する必要があります。
そして、株式を保有していると、定期的に配当が発生することとなります。
この配当についても、相続税の課税対象になる場合があります。
配当については、申告漏れになってしまうことが多いですので、見逃しのないように注意する必要があります。
2 配当について相続税が課税される場合
前提として、配当基準日と配当確定日の2つの概念を押さえておく必要があります。
・ 配当基準日
その日の株式を保有していることにより、配当を受ける権利が得られる日のことをいいます。
基本的には、配当のある四半期末になります。
多くの場合、3月31日、6月30日、9月30日、12月30日のいずれかです。
・ 配当確定日
配当金交付の効力が発生する日のことをいいます。
つまり、配当金交付に関する株主総会決議が行われる日です。
いつが配当確定日になるかは、株主総会決議のスケジュールによって変わってきます。
配当について相続税が課税される場合は、以下の2つの場合です。
① 被相続人が亡くなったのが、配当基準日(配当のある四半期末)の翌日から、配当確定日(配当についての株主総会の日)までである場合
この場合、被相続人は、配当期待権を持っていたこととなり、配当期待権が相続税の課税対象となります。
② 被相続人が亡くなったのが、配当確定日(配当についての株主総会の日)の翌日から、配当の受取日の間である場合
この場合、被相続人には、未収配当金があったこととなり、未収配当金が相続税の課税対象となります。
なお、被相続人が亡くなったのが配当基準日(配当のある四半期末)以前である場合は、配当は、被相続人ではなく、相続人の所得と考えられますので、被相続人についての相続税の課税対象にはならないこととなります。
また、被相続人が亡くなったのが、配当の受取日よりもあとである場合は、その配当は、被相続人の口座に入金済みでしょうから、そもそも配当についての課税を考える必要がありません。
以上から、配当について相続税が課税されるのは、被相続人が亡くなったのが、配当基準日(配当のある四半期末)の翌日から配当の受取日の間である場合ということになります。
この場合には、配当期待権か未収配当金のいずれかで課税がなされることとなります。
3 配当期待権、未収配当金の評価方法
配当期待権、未収配当金の評価方法は、いずれも、以下のとおりです。
配当金額-源泉徴収される所得税等に相当する金額
源泉徴収される所得税等に相当する金額は、2020年ですと、20.315%になります。
したがって、配当期待権も、未収配当金も、配当金額から20.315%を差し引いた金額で評価されることとなります。
未成年者とその親が相続人になった場合の相続税申告
1 未成年者とその親が相続人になった場合

被相続人が亡くなり,その配偶者と子が相続人になることがあります。
被相続人が若くして亡くなった場合は,子が未成年であるということが,しばしばあります。
この場合には,未成年者とその親が相続人になります。
このような相続関係で相続税申告を行う際には,注意しなければならないことがあります。
2 遺産分割協議を行うために,特別代理人が必要になる
相続税申告を行う際には,遺産分割協議を成立させ,協議後の分割割合で申告を行うことが考えられます。
今回は,未成年者とその親が相続人になりますので,両者で遺産分割協議を行うこととなります。
しかし,ここで注意しなければならないことがあります。
未成年者は,単独では法的行為を行うことができず,親が代理人となって法的行為を行うこととなっています。
そうすると,今回,遺産分割協議の当事者が,未成年者の代理人である親と,親自身になってしまい,有効な遺産分割協議ができないこととなってしまうのです。
このため,有効な遺産分割協議を行うには,前提として,未成年者に特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人は,未成年者の代理人として,遺産分割協議を行うことができます。
また,未成年者に代わって相続税申告を行うこともできるとされています。
3 特別代理人を選任する際の注意点(未成年者は法定相続分以上の財産を取得)
特別代理人を選任するに当たっては,何点か注意しなければならないことがあります。
特別代理人は家庭裁判所の審判によって選任されることとなっています。
家庭裁判所に必要な書類を提出し,審判を得る必要がありますので,特別代理人を選任するまで,1から2か月の期間を要します。
このため,相続税の申告期限の直前に手続を開始しても,間に合わない可能性が高いですので,早めに手続を行う必要があります。
次に,特別代理人が選任されたからといって,どのような遺産分割協議でもできるというわけではありません。
特別代理人は,未成年者の法律上の権利を保護しなければならないこととなっています。
このため,基本的に,遺産分割協議の結果,未成年者が法定相続分以上の財産を取得するものとする必要があります。家庭裁判所は,基本的に,未成年者が取得する財産が法定相続分を下回る遺産分割協議を行うことを認めていません
今回ですと,未成年者の相続分は2分の1になりますので,未成年者が2分の1以上の遺産を取得するとの内容の遺産協議を成立させる必要があります。
4 配偶者の税額軽減(配偶者控除)を利用するため,すべての遺産を親が取得するとの内容の遺産協議を行うことはできないのか?
ところで,未成年者が2分の1以上の遺産を取得しなければならないとの点については,相続税の負担を考えると,大きな問題があります。
配偶者が取得した財産については,1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい金額までは,相続税が課税されないこととなっています。
このような制度があるため,遺産総額が1億6000万円以下であれば,配偶者がすべての遺産を取得するものとすれば,相続税は課税されないこととなっています。
このため,遺産について,2分の1を未成年者が取得し,2分の1をその親(つまり被相続人の配偶者)が取得するものとすると,親が取得した2分の1については相続税が課税されないこととなりますが,未成年者が取得した2分の1については相続税が課税されることとなってしまいます。
それでは,このような事態を避ける目的で,すべての財産を親が取得するとの遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか?
家庭裁判所は,相続税の負担を避けるという目的であっても,未成年者にとって不利な遺産分割協議を行うことは認めていません。
したがって,すべての財産を親が取得するとの遺産分割協議を行うことは,できないこととなります。
5 配偶者の税額軽減(配偶者控除)を利用するための対応策はないのか
それでは,未成年者とその親が相続人になる場合は,配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いる余地が完全になくなってしまうのでしょうか?
対応策としては,次のようなものがあります。
これまでは,遺産分割協議を行う前提で話を行ってきましたが,10か月の申告期限内では,一旦,未分割のままで申告を行うことも考えられます。
未分割のままで申告を行う場合は,未成年者が法定相続分どおりの2分の1,その親が法定相続分どおりの2分の1について,相続税を納付する必要があります。
この段階では,配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いることはできませんので,未成年者もその親も相続税を納付する必要があります。
そして,未成年者が成人に達したあと,成年者とその親とで遺産分割協議を行います。
この場合は,成年者は単独で遺産分割協議を行うことができますので,どのような内容の遺産協議を行うこともできることとなります。
このため,成年者とその親との間で,すべての財産を親が取得するとの遺産分割協議を行うこともできることとなります。
親(被相続人の配偶者)がすべての遺産を取得するとの遺産分割協議が成立すれば,配偶者の税額軽減(配偶者控除)を用いることができますので,更正の請求を行い,相続税の全額の還付をうけることができます。
もっとも,このような方法には,いくつかの限界があります。
まず,申告期限内に未分割で申告を行いますので,未成年者もその親も,一旦は,相続税を納付する必要があることとなります。
また,未成年者が成人するまで,遺産を未分割にしておく必要もありますので,基本的には,預貯金の出金も不動産の名義変更もできないままになります。
さらに,更正の請求については,時間的な限定があり,申告から更正の請求まで長期間が経過してしまうと,更正の請求ができなくなるおそれもあります(詳しくは,3年以内の分割見込書についての説明をご覧ください)。
弔慰金,花輪代,葬祭料と相続税
1 弔慰金,花輪代,葬祭料とは何ですか?

被相続人が亡くなった場合に,会社や雇用主から支給される金銭があります。
代表的なものは,死亡退職金です。
これは,被相続人が存命であれば支払われるはずであった退職金を,被相続人の代わりに,遺族に対して支給するものです。
死亡退職金以外に,遺族を慰める目的で,金銭の支払がなされることがあります。
このような金銭を,弔慰金といいます。
弔慰金以外にも,花輪代,葬祭料等,葬儀の関係で支給される金銭もあります。
2 どこまでが相続税の課税対象になるのでしょうか?
弔慰金,花輪代,葬祭料については,以下の非課税限度額を超える部分については,死亡退職金とみなされ,相続税の課税対象になります。
・ 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき→普通給与の3年分
・ 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき→普通給与の半年分
ここでいう普通給与とは,俸給,給料,賃金,扶養手当,勤務地手当,特殊勤務手当等の合計額のことをいいます。
基本給のみではなく,扶養手当,勤務地手当,特殊勤務手当等も普通給与に加算できます。
他方,残業代,賞与については,普通給与には含まれません。
それでは,以下の具体例では,どのようになるのでしょうか?
・ 法定相続人は2人
・ 会社から,死亡退職金として2000万円が,弔慰金として500万円が支給
・ 普通給与は月40万円
・ 業務上の死亡ではない
このような場合は,以下のように計算されると考えられます。
弔慰金のうち,死亡退職金と見なされる部分→500万円-(40万円×6か月)=260万円
死亡退職金の額→2000万円+260万円=2260万円
相続税の課税価格に含まれる死亡退職金→2260万円-500万円×2人=1260万円
※ 死亡退職金については,法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額があります。
3 業務上の死亡かどうかの判断基準
業務上の死亡の場合は,弔慰金,花輪代,葬祭料の非課税限度額が普通給与の3年分となりますので,業務上の死亡でない場合と比較して,非課税限度額が大きくなります。
それでは,業務上の死亡に該当するかどうかは,どのように判断されるのでしょうか?
一般論としては,業務に起因する死亡であるか,業務と相当因果関係のある死亡である場合は,業務上の死亡と判断されます。
言い換えると,業務遂行中に死亡した場合,業務に起因する事故,疾病により死亡した場合ということになります。
通勤中の死亡についても,業務上の死亡と判断されますので,普通給与の3年分が弔慰金,花輪代,葬祭料の非課税限度額となります。
4 共済組合から受け取った弔慰金,埋葬料は,相続税の課税対象になるのでしょうか?
会社,雇用主から受け取る弔慰金等以外に,共済組合から弔慰金等が支給されることがあります。
このような弔慰金等としては,以下のようなものがあります。
・ 国家公務員共済組合法に規定する弔慰金,埋葬料
・ 地方公務員等共済組合法に規定する弔慰金,埋葬料
・ 私立学校教職員共済法に規定する弔慰金,埋葬料
このような共済組合から支給される弔慰金,埋葬料については,相続税法の規定により,死亡退職金とは見なされないこととなっています。
したがって,これらの弔慰金,埋葬料については,相続税が課税されることはないこととなります。
このように,共済組合から支給される弔慰金等については,会社,雇用主から支給される弔慰金等とは扱いが異なりますので,注意が必要です。
税理士による相続人の調査
1 相続人調査が必要になる場合
税理士は、相続税申告にあたって、相続人調査を行うことがあります。
相続人が確定していなければ、相続税の計算を行うことができず、申告を行うことができないため、相続税申告を行う税理士にとって、相続人調査は必要不可欠の前提となります。
2 相続人調査の方法

それでは、相続人調査はどのようにして行われるのでしょうか?
相続人調査は、基本的には、市区町村役場で戸籍を取得することにより行われます。
この時、どのような戸籍が必要になるかは、相続関係によって違ってきます。
もっとも、どのような相続関係であったとしても、以下の戸籍は必ず必要になってきます。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
・ 相続人の現在の戸籍
戸籍については、本籍地のある市区町村役場、本籍地のあった市区町村役場で発行してもらう必要があります。
このため、本籍地の変更が繰り返されていると、複数の市区町村役場で、戸籍を発行してもらう必要があります。
また、遠方の市区町村役場であっても、本籍地があるまたは本籍地があった以上、その役場で戸籍を発行してもらう必要があります。
戸籍自体は、郵送で取得することもできますが、1つ1つの市区町村役場で、必要書類を確認・手配し、戸籍を送ってもらうことも、かなりの手間になってきます。
また、古い戸籍については、手書きで作成されており、どの部分に着目すれば相続関係が確認できるかが分かりにくいことがありますし、そもそも、読みにくい文字で手書きされていることもあります。
以上から、必要な戸籍をもれなく取得することは、かなりの手間になります。
3 自分で集めることができない場合は?
それでは、自分で必要な戸籍を集めることができない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
この場合は、申告について委託を受けた税理士であれば、本人に代わって、必要な戸籍を取得することができます。
税理士は、職務上請求という手段を用いることができ、申告等を行うために必要がある場合には、戸籍を取得することができるからです。
相続人調査に時間を割くことができない等、相続に調査についてお困りのことがありましたら、合わせて、税理士にご相談いただけましたらと思います。