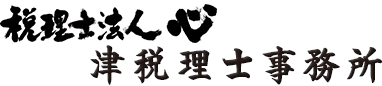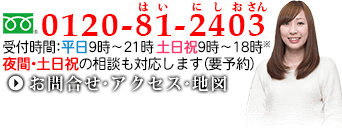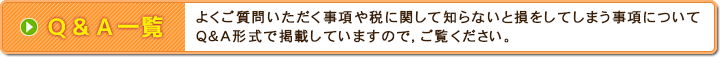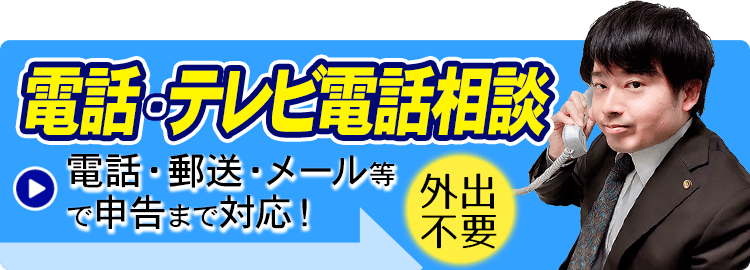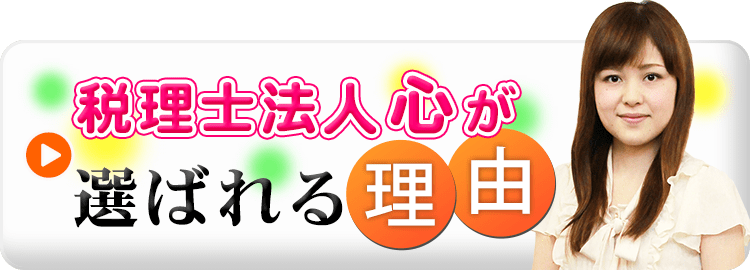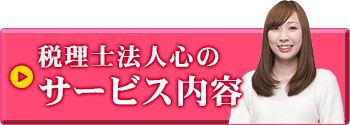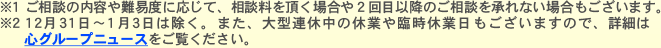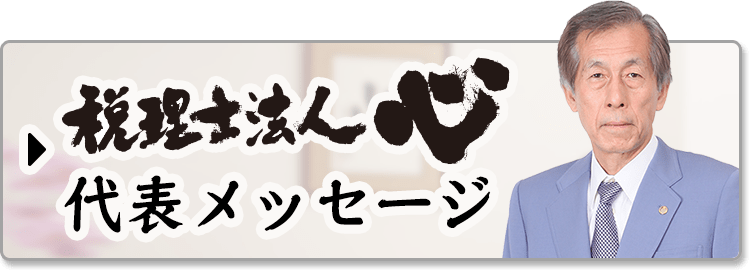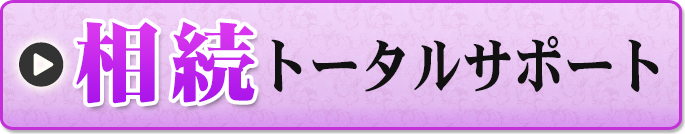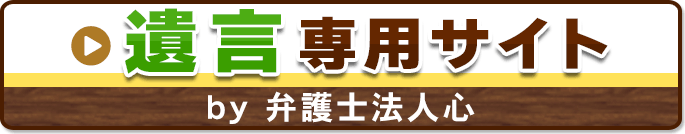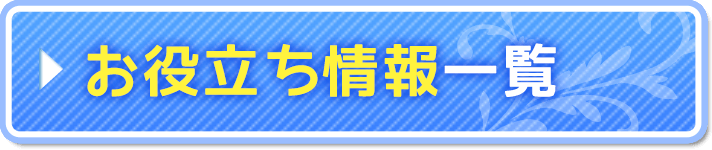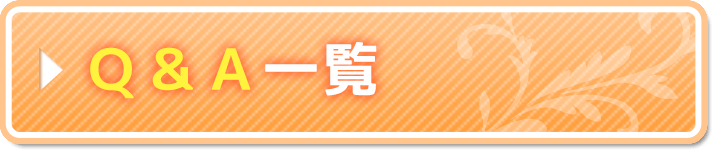個人事業主が免税事業者となる要件
1 消費税の免税事業者
個人事業主として事業活動を行い、売上が発生すると、売上について、消費税を納税する義務が発生することとなります。
ただ、一定の期間における売上高が1000万円以下である等の要件を満たせば、免税事業者となり、消費税が課税されないこととなる可能性があります。
ここでは、個人事業主が免税事業者となる具体的な要件を説明したいと思います。
2 免税事業者となる要件
免税事業者となる要件は、以下の2点です。
手続についても留意すべき点があるため、合わせて説明します。
① 前々年の1月1日から12月31日までの売上高が1000万円以下であること(要件①)
まず、前々年の1月1日から12月31日まで(基準期間)の売上高に着目します。
この期間の売上高が1000万円以下であることが1つ目の要件になります。
たとえば、令和7年の売上について、消費税を免税にすることができるかどうかを検討する場合は、前々年である令和5年の1月1日から12月31日までの売上に着目します。
この間の売上が1000万円以下であれば、免税事業者となる1つ目の要件を満たすこととなります。
なお、国外取引、出資に対する配当等、消費税が課税されない売上がある場合は、これらの売上は除外して、1000万円以下になるかどうかを判断することとなります(後述の特定期間の売上についても同様です)。
② 前年の1月1日から6月30日までの売上高が1000万円以下であること(要件②)
次に、前年の1月1日から6月30日まで(特定期間)の売上高に着目します。
この期間の売上高が1000万円以下であることが2つ目の要件になります。
令和7年の売上について、消費税を免税にすることができるかどうかを検討する場合は、前年である令和6年の1月1日から6月30日までの売上が1000万円以下であれば、2つ目の要件も満たすこととなります。
③ 手続
すでに免税事業者であるときは、特に手続を行うことなく、引き続き免税事業者となることができます。
また、後述しますが、新規開業の場合も、特に手続を行うことなく、免税事業者となることができます。
また、売上高の増加により、一時的に①、②の要件を満たさなくなり、課税事業者となった場合で、その後、売上高が減少し、①、②の要件を満たすこととなった場合については、自動的に免税事業者となります。
ただ、この場合は、消費税の免税事業者でなくなった旨の届出書を税務署に提出しなければならないこととなっています。
とはいえ、消費税の免税事業者でなくなった旨の届出書の提出は、税務署に対する報告のためになされるものであり、免税事業者となるための手続的な要件ではないため、届出書を出し忘れたとしても、免税事業者として扱ってもらうことができます。
詳しくは後述しますが、①、②の要件を満たしているため、免税事業者になっている場合であっても、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、あえて消費税の課税事業者になることができます。
その後、やはり免税事業者に戻りたいとなった場合については、免税としたい期間の前日までに、消費税課税事業者選択不適用届出書を税務署に提出する必要があります。
この届出書の提出は、免税事業者となるための手続的な要件になります。
3 消費税課税事業者選択届出を提出していないこと
①、②の要件を満たしており、免税事業者になることができる場合であっても、消費税課税事業者選択届出書を提出すると、消費税の課税事業者になってしまいます。
つまり、消費税課税事業者選択届出を提出していないことも、消費税の免税事業者となるために必要な要件となってきます。
あえて消費税の課税事業者になることがあり得るのかと思われるかもしれませんが、あえて消費税の課税事業者となることによってメリットが存在する場合があるため、あえて消費税の課税事業者となる選択肢が取られることがあります。
具体的には、以下のとおりです。
⑴ インボイスを発行したい場合
取引先からインボイスの発行を求められた等の理由により、インボイスを発行できるようにしたいと考えることがあります。
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者になると、適格請求書発行事業者になった時から消費税が課税されることとなります。
このため、インボイスを発行できるようにした場合には、もはや、消費税の免税事業者にはなれないこととなります。
⑵ 消費税の還付を受けたい場合
消費税は、売上に課税される消費税と仕入れに課税される消費税との差額を納付する制度になっています。
そして、仕入れに課税される消費税が売上に課税される消費税を上回るときは、仕入れに課税された消費税を還付してもらうことができます。
ここでいう仕入れには、開業費用や設備投資も含まれます。このため、多額の開業費用や設備投資を要した場合は、これらに課税される消費税も大きな金額になりますので、仕入れに課税される消費税が売上に課税される消費税を上回る可能性が高まります。
ただ、消費税の還付を受けるためには、消費税の課税事業者となっておく必要がありますので、この場合も、消費税の免税事業者にはなれないこととなります。
上記⑴、⑵のような事情がある場合には、➀、➁の要件を満たしており、免税事業者になることができる場合であっても、あえて消費税の課税事業者となるとの選択肢が取られる可能性があります。
この場合には、消費税の課税事業者となることを希望する年度が始まる日の前日までに、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、消費税の課税事業者となります(ただし、適格請求書発行事業者選択届を提出する場合は、同時に消費税課税事業者選択届出を行うことができ、その登録日から課税事業者として扱われることとなります)。
以上を裏返すと、消費税の免税事業者になるためには、消費税課税事業者選択届出を提出しないこととする必要があり、そのために、インボイスを発行することを断念したり、消費税の還付を受けることを断念したりする必要があることとなります。
4 消費税課税事業者選択届出を提出したあとに、免税事業者に戻るための要件
上記⑴、⑵等の事情により、消費税の課税事業者となったとしても、やはり免税事業者に戻りたいとなった場合は、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、免税事業者に戻ることができます。
この場合は、免税としたい期間の前日までに、消費税課税事業者選択不適用届出書を税務署に提出する必要があります。
ただ、消費税課税事業者選択届出書を提出し、消費税の課税事業者になってから2年間は、免税事業者に戻ることができないこととなっているため、注意が必要です。
たとえば、令和6年1月1日から消費税の課税事業者になっている場合は、令和7年12月31日までは免税事業者に戻ることができず、令和8年1月1日以降に消費税の免税事業者に戻ることができ、同日以降の売上について、消費税を免税とすることができることとなります。
このように、課税事業者となることを選択した後に、免税事業者になることを希望する場合は、免税事業者となる要件が厳しくなります。
5 新規開業の場合
新規開業の場合については、基本的には消費税の免税事業者になることができるという話がなされることがあります。
というのも、新規開業から2年間は、前々年の売上は存在しないこととなりますので、免税事業者の基準期間の要件を満たすことができることとなるからです。
ただ、新規開業から1年が経過すると、前年の1月1日から6月30日までの売上が存在する可能性があり、この期間の売上高が1000万円を超える場合は、特定期間の要件を満たさないこととなりますので、免税事業者になることはできません。
たとえば、令和6年4月1日に新規開業した場合を考えたいと思います。
新規開業の2年後である令和8年4月30日までは、前々年の売上高が存在しないため、基準期間の要件を満たすこととなりますが、令和8年5月1日以降は、前々年の売上高が存在し、これが1000万円を超えてくる可能性があることとなります。
このため、令和6年度の売上(令和6年4月1日から令和8年12月31日までの売上)が1000万円を超えるときは、基準期間の要件を満たさないこととなり、令和8年以降の売上(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの売上)について、消費税が課税されることとなる可能性があります。
また、新規開業の1年後である令和7年4月30日までは、前年の売上高が存在しないため、特定期間の要件も満たすこととなりますが、令和7年5月1日以降は、前年の売上高が存在し、これが1000万円を超えてくる可能性があることとなります。
このため、令和6年度の上半期の売上(令和6年4月1日から令和6年6月30日までの売上)が1000万円を超えるときは、基準期間の要件を満たさないこととなり、令和8年以降の売上(令和8年1月1日から令和8年12月31日までの売上)について、消費税が課税されることとなる可能性があります。
なお、新規開業の場合であっても、先述のとおり、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより、あえて消費税の課税事業者になることができますので、その場合は、消費税が課税されることとなります。